連載1-2/「良い学生」とはどんな人?学生の持ち味の発見から学生団体「HIT-ALPs 」誕生【広島工業大学】
- odlabo
- 2025年2月25日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年4月11日
広島工業大学の工学部・電気システム工学科では2019年より新入生オリエンテーションにチームビルディングプログラム「自己の探求」を活用していただいています。プログラム実施の際には教員もグループワークに参加しており、学生の個性や可能性を発見できる機会が先生方にも大きな気づきを与えているようです。その気づきから、同学科では、電気への純粋な探究心や「何かをつくりたい」という熱意を持つ学生たちが主役となるこの「HIT-ALPs」という活動がスタートしていいます。チームビルディングプログラムの導入をリードした川原耕治先生(工学部 電気システム工学科 教授)は、こうした学科の活性化をどのように感じておられるのか、話を聞いてみました。(全3回の2回目)

――オリエンテーションゼミで行う「自己の探求」には川原先生も参加されているんですか?
川原先生 毎年ではないですが、2年に1回は参加するようにしています。自分が担当する学生についてはなんとなくわかるようになるメリットはあるかなと思いますね。教員に対しては、学生が教員に対するハードルを下げる機会になるので、同じ目線に立って一緒にやったほうが良い、とは言っています。
――新入生ガイダンスを宮島での一泊研修で行っていた頃は、先生方はどうされてたんですか?
川原先生 1年生にグループを組ませて、各グループに上級生を1人、2人割り当てて、宮島を散策してもらいました。教員も同行しますが、教員は教員で勝手に過ごしているような感じでした
――サポート役を務める上級生はどのように選んでいたんですか?
川原先生 基本的には「良さげな人」を選ぶんですけど、こちらがいいと思って声をかけた学生よりも、あまり期待していなかった学生のほうがよかったりもするんですよね。我々は成績がよい学生を選んでしまうんですけど、ああいう場面では必ずしもそれがよいとは限らないようです。
――人それぞれにいろんな持ち味がありますからね・・・先生方にとっては、学生任せの頃と比べると個々の学生の様子がよくわかるというメリットもあるようですが、導入後に先生方に何らかの変化は感じますか?
川原先生 「自己の探求」をとおして、我々が一対多で教える時よりも学生の状況が深くわかるようになりました。授業ではそこまで各個人にかかわるような場面がないですから。1年生ってみんなおとなしそうに見えるんですけど、「自己の探求」で1日付き合ってみると、活動的でユニークな考えをもっているような学生がいたりするんです。「そういう学生がいるんだったら、場を提供したら何かしてくれそうじゃないか」っていう、我々に気づきと勇気を与えてくれる場になりました。それがHIT-ALPsと言う活動の立ち上げにつながっていったのです。
――今までは「集団」として大掴みで捉えていたものが、「個」の輪郭がくっきりと見えて、先生方も学生さんに対する気づきがあったのかもしれませんね。
HIT-ALPsについても、簡単で構いませんので、教えていただいてもいいでしょうか。
川原先生 電気システム工学科の次のステップを考えた時に、このプログラムでできた先輩後輩のつながりを含めて、学科の一体感を出そうとするなら、もうちょっと踏み込んだ組織をつくらないと難しいんだろうなとも感じるようになりました。
「電気らしい」何かやりたいという思いから、村上修二先生(同学科教授)たちが中心となってHIT-ALPs※を立ち上げてくれました。勉強ができる人に限らず、「電気」を題材に、電気に関する疑問を解決したいとか、便利なものや仕組みをつくってみたいとか、そういう思いを起点として、賛同する人とグループをつくって一緒に考えて、実現していこうという活動です。
ベースにあるのは、進め方も含めて学生が自分たちで考える活動であるということ。仲間を増やしたければ、活動の面白さを他人に伝えるプレゼン能力も必要になっていくでしょうし。単なる自己満足にとどまらず、他の人にもうまく伝えたくなるような活動になっているのがポイントではないでしょうか。
※HIT-ALPs(ヒットアルプス)
電気システム工学科の学生プロジェクト。「活動を通じて、高校生や中学生、小学生に電気の面白さを伝えたい」という思いを持つ学生たちの組織
(参照リンク:広島工業大学ホームページ)https://www.it-hiroshima.ac.jp/news/2024/10/hit-alps.html
――具体的にはどんな活動が行われているのですか?
川原先生 例えば、小中学生に対する理科教室などですね。電気の面白さを伝えるために、近くの公民館に行って教えたりもしています。僕が直接関わっているわけではないので、詳細は担当の村上先生に聞いてみてください。
――これまでは、貴学には学生主体の活動組織はなかったのでしょうか?
川原先生 どこの大学でもオープンキャンパスを学生に手伝ってもらったりしますよね。学科でも上級生に1、2年生の数学の補講や実験に関与してもらうことも多いのですが、TAやSAには、やはり成績のいい学生を選んでしまいます。しかし、勉強も大切なんですけど、電気システム工学科では、成績のいい学生=教えるのがうまいとかコミュニケーションがスムーズかどうかは話が別なようです。
成績のいい学生に対しては、本学では「発展トラック」※というプログラムが設けられているのですが、そういう枠組みもあまり活性化していません。オープンキャンパスなど高校生が集まるイベントでも、成績のいい学生を中心に選んで対応してもらうのですが、それほど活発ではない雰囲気です。
その一方で、学生とかかわるうちに、成績じゃない面でもっと元気な学生がいることはわかっていました。大学全体の枠組みにはないとしても、学科として、そういう学生がもっと活躍できる場をつくることができれば、波及効果も期待できます。それで、村上先生やラーニングバリューさんとも相談しながら、そういう枠組みをつくることを考え始めたんです。
(参照リンク:広島工業大学ホームページ⇒https://www.it-hiroshima.ac.jp/about/gp/develop-track/)
――学科でそういう活動を始めるにあたって、他の先生方の反応はいかがでしたか?
川原先生 最初は、「学生がちゃんとやるのかな?」という感じでした。最近はアルバイトをする学生が多いので、僕もわざわざ時間をつくって集まる学生がどれくらいいるんだろうっていうのは疑問でした。でも、実際に活動しているんですよね。最初のきっかけは教員が与えたものかもしれませんが、僕が思ってる以上に乗ってくる学生がいました。
――学生の動機に火をつけた、ということになるんでしょうか。
川原先生 そこは村上先生がうまいんだと思いますよ。村上先生がいなかったら多分できてないと思いますね。
――ちなみに、単位の出る活動なんですか?
川原先生 いえいえ、全然関係ありません。ただ、多少の費用はかかるので、賛同を得られる企業さんからご協力をいただく仕組みも用意して、少しずつ、広く薄く募って継続することを考えています。
――川原先生のお話を伺ってると、視点が「全体の活性化」にあるように感じます。「こういう学生がいて悩んでいる」という個の話ではなく、もっと全体を見ておられるようですね。
川原先生 もちろん個別にもいろんな対応をしなきゃいけないので難しいことではあるのですが、我々も限られた資源で教育を行っています。どこに資源を使うかを考えた時に、個別に対処するよりも、枠組みを使って、あわよくば勝手に育ってくれたら・・・とも思うんです。個別に対処しても他には波及しないとなると、やっぱり仕組みとしてそういうものがある方がよいのではないか、と。立ち上げるのも継続するのもずっと大変だと思うんですけど、枠組みが軌道に乗った時には、個別に対処するよりもはるかに多くの得るものがあるんだろうなと思うんです。
――冒頭でおっしゃっていた、新入生ガイダンスで「宮島に行く」という仕組みよりも、もっといい仕組みを求めて、弊社の「自己の探求」を見つけて採用してくださったということですね。
川原先生 「同じ釜の飯を食う」なんていうのは古い考え方なんですよ。今どきの学生は大学に来る動機もさまざまで、親や先生に言われたから来たという学生もいます。なのに、大学側は学生に積極的に活動してほしいのでそういう場をつくるんですけど、おそらく全員がそれをやりたいとも思っていないんです。そんな中で、多様な学生が取り組める仕組みをつくれば、参加する学生はもちろん元気になるし、参加していない人も、参加する人が身近にいることで何らかの影響を受けたり、このままでいいんだろうかどうだろうかっていう考えたりする機会にもなるでしょう。そういったことも含めて、学生主体で、学生が主役になる仕組みをつくるメリットは大きいと思います。
※肩書・掲載内容は取材当時(2024年12月)のものです。


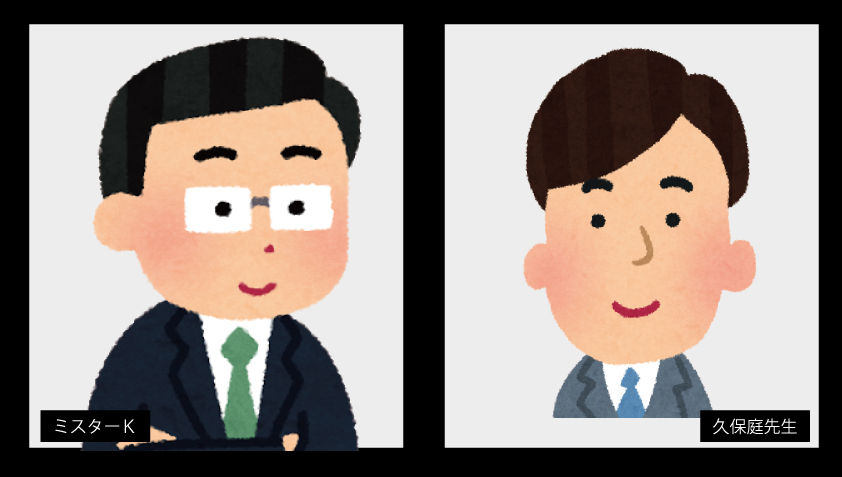
コメント