連載2-1/ベンチャー起業から大学教授へ!村上先生の異色キャリアが導く学生活性化のヒント【広島工業大学】
- odlabo
- 2025年3月25日
- 読了時間: 7分
更新日:2025年4月11日
新入生の大学適応をスムーズにするため、広島工業大学 電気システム工学科では弊社のチームビルディングプログラム「自己の探求」を活用していただいています。前回まではプログラム導入の背景やねらいについてご紹介してきましたが、連載第2回は、その取り組みをきっかけに始まった学生の主体性を引き出すためのユニークな活動に焦点を当てていきます。お話をお伺いしたのは、企業の世界で活躍した後、教育研究の世界へと転身された、村上修二先生(電気システム工学科教授)。学生の成長を促す土壌をいかに培おうとしているのかお聞きしました。(全3回の1回目)

――まずは、村上先生のキャリアについてお伺いしたいと思います。先生の前職は?
村上先生 ここに入る前は、通信用のLSIを設計、開発する会社に勤めていました。私はちょっと経歴が変わっていまして、大学卒業後は大手電機メーカーに入社して、アメリカに2年間留学させてもらい、通信用LSIの開発に携わるようになりました。その技術で仲間と創業することになりました。
――いわゆるベンチャービジネスですね。
村上先生 まさにそうです。16年ほど働いたのですが退職することになり、かつて取得した博士号を役立てて、若い人の教育研究に携わってみたいという思いが湧いてきて。この大学に応募して、2016年4月から教員になりました。電気システム工学はエネルギーシステムと、情報通信システム、コンピューターシステムの3つで成り立ってるのですが、私は主に情報通信の方を担当していいます。
――先日、川原先生にいろいろとお話を伺いしたのですが、川原先生の教務部長時代に退学者の問題から、新入生オリエンテーションの内容を見直すことになり、弊社のチームビルディングプログラム『自己の探求』の導入をしていただいたと聞いています。その辺りの経緯を村上先生はご存知ですか?
村上先生 私の記憶では、御社のHさんが来られたのがきっかけだったかと思います。その時すでに『自己の探求』を導入していた情報学部の先生から本学科の課題をお聞きになられたHさんに、いろいろと話を伺って、面白そうだったので電気システム工学科の中で提案したんだと思います。『自己の探求』については、川原先生もすでにご存じで、実際にプログラム体験もされていらっしゃいましたし、他の先生方も非常に賛同されて、そこから話がとんとんと進んでいったと記憶しています。
――現在は、2日間の新入生オリエンテーションのうち1日目に『自己の探求』を行って、2日目には電気システム工学科恒例のグループごとの工作実習(グループごとに厚紙と割り箸と輪ゴムを材料にして、ゴム動力で動く車を作り走行距離を競う実習)を実施されているんですよね。
村上先生 2日目の工作実習は、それまで宮島で宿泊で行っていた新入生オリエンテーションでも行っていました。学科の先生方の大半が「宮島でもやっていた工作実習は続けるべきだ」という意見だったんで、それを組み合わせて行うことにしたんです。
――村上先生は『自己の探求』にどのような印象を持ったか教えてもらってもいいですか?
村上先生 びっくりしました。『自己の探求』を初めて導入した時は、新入生が入学して2週間ぐらい経った時期に行いました。学生同士はまだ全然知り合いもいないような雰囲気で、プログラムが始まる時は教室がシーンとしてるんですね。一体どうなるんだろう、このまま静かに一日が終わるのかなと思ってたら、お昼休みにはみんながドーンと爆発するように盛り上がっていて。その日が終わる頃にはみんなでワイワイガヤガヤと非常に仲良くなっていて。1日でこんなに変わるのか、これは今後もぜひ続けさせていただきたいということで、ずっとお願いしているんですよ。
――その雰囲気は、宮島での一泊研修の時とは違っていますか?
村上先生 宮島でも結構盛り上がっていたんですよ。卒業生からは、少ないけれど仲のいい友達ができる感じだったとは聞いてはいました。しかし一緒に寝泊まりするメンバーの中でも、その輪に入れない学生も出てきていたのかなという気はします。2、3人の仲間とはぐっと仲良くなるけど、それが全体には広まっていかない。それに対して『自己の探求』は、ちょっと強制力があるというか、最初の「記者会見」にしろ、その後の「総当たりインタビュー」にしろ、一応グループ全員と話ができますよね。ちゃんとルールを作ってやらせるやり方がいいんだろうなと思います。
――村上先生も学生と一緒にプログラムを体験されたわけですよね。学生さんと接していて感じることはありましたか?
村上先生 私は元々学生と話すのが好きなので、楽しいな、というところですね。「総当たりインタビュー」で一通りの学生と会話すると、人柄がわかってくるんですよ。ただ、残念なのは、その時だけで終わっちゃうんですよね。それが終わるとまた、教員と学生に戻るっていうか、離れちゃうんですよね。もう少しあのような機会を続けられれば、もっと仲良くなれるんだろうなとは思うんですけどね。そこは残念なところです。
――他の先生方の反応はいかがですか?
村上先生 みなさんに協力していただけています。『自己の探求』の終了後のファシリテーターの方々との懇談にも先生方は残ってくださったりして、非常に前向きに感じていただけているようです。
――プログラムにはサポート役として先輩学生も参加してくれていますよね。彼らの反応はいかがですか?
村上先生 指導学生のことですね。毎年確認しているわけではないのですが、楽しいようですよ。今年は特にHIT-ALPs(新たに立ち上がったプロジェクト)の学生がやってくれたのですが、そう言っていました。
―― 「自己の探求」は、チューターグループ単位で実施しますが、その後も「社会実践科目」や学生生活ではチューターグループでまとまることが多いと聞いています。この科目では、授業は1年生、2年生は別々に受けるのに、クォーターごとの振り返りだけは1年生・2年生合同で、知らない者同士で4人グループをつくって行う仕組みになっていますよね。そのことについてはどのように思われますか?
村上先生 ねらいはいろいろとあるのですが、1,2年生をごちゃまぜにするという方法は、ラーニングバリューさんからのアドバイスで始まったことなんです。学生にとっては、学ぶことだけでなく、コミュニケーション能力をつけるというのも、とても大事なことなんですね。チューターグループの人としか話さないというのは良くないので、できるだけ知らない人とも話をできるようにしようということで、こういう方法をとっています。
そもそも社会実践科目は、2年生が1年生を指導しながらコミュニケーションを取ることを目的としていたんです。当初は、第2クォーター、第3クォーターの実験の中でそういうことをやろうとしていた面もあったのですが、現実的には難しいんですね。なので、今はもう実験自体は2年生と1年生で完全に別のテーマで行っています。でも、最後の振り返りだけは、1年生、2年生をミックスしてグループを作ってやるようになったんです。
――学生さんの反応はいかがですか?
村上先生 アンケートの結果では、いつも満足度が高いです。実際、教室での様子も、みんな楽しそうに話をしていますんでね。2年生は1年生の時に体験したプロセスなので、1年生に指導とまではいかないにしても、いろいろとアドバイスをしてるような状況はあちこちで見受けられます。大体1年生からの質問といえば「どの科目が難しい?」ですから。2年生は「この科目は大変だからちゃんと頑張って勉強しておかないと」などと言っていますよ。
――必修科目で、1年生全員が先輩と接点を持てる場があるのはメリットですよね。授業に対する不安もちょっと減るようなこともあるんでしょうね。
村上先生 あると思いますね。1人で抱えこんでしまうと、どんどん悪い方向に行ってしまうので、やはりこう、人と話すのはとても大事だと思います。そこで答えが出るわけではないのでしょうけど、相談すると若干不安が解消される面はあると思います。しかも、相手は学年が1つしか変わらない先輩なので聞きやすいですよね。
※肩書・掲載内容は取材当時(2024年12月)のものです。


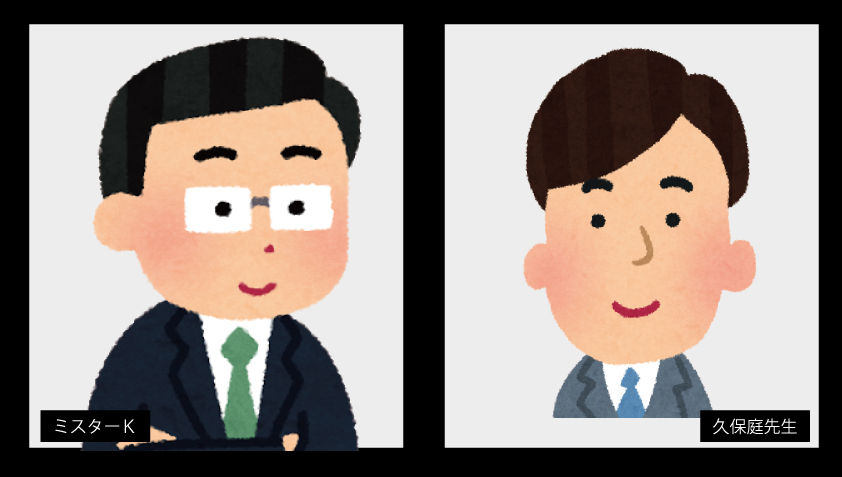
コメント